IPS CELL THERAPY
iPS細胞治療
#細胞移植 #自家移植と他家移植 #眼病 #心臓病 #脳神経疾患 #血液疾患 #免疫細胞の活用

iPS細胞治療 × iPS Private Bank自分自身の細胞で“初期化”する、
次世代医療。
最先端治療から始まる“選ばれた医療”
iPS細胞治療は、自身の細胞を“生まれたて”の状態へと初期化し、
最も純粋で無垢な状態から再び身体に戻す、次世代の再生医療です。
拒絶反応のない、ナチュラルな若返りと回復を可能にします。
これは、他のどの再生治療でも実現できない、唯一無二のアプローチです。
iPS Private Bankでは、
自分自身の細胞を生まれた直後の一番ピュアな状態にリバースし、
プラベートバンクでいつでも利用可能な状態で保管いたします。
アイ・ピース社が認めた国内でも限られた機関だけで行える治療となります。
国内でも限られた機関だけが
実施できる
厳選された再生医療
-

当院は、細胞加工技術において世界最高水準のiPS治療研究ラボ「アイ・ピース社」と正式提携。

-


投与に用いる細胞は、GMP準拠・不純物完全除去・高エクソソーム濃度で管理。
-
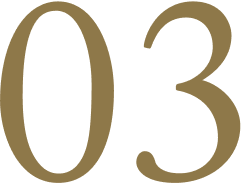
治療設計は、院内医師チームと提携細胞研究者が共同でプランニング。

-


完全非公開スケジュールで、プライバシーと信頼性を徹底。
-

治療後には、細胞の状態証明書と結果レポートをお渡しします。

iPS Private Bank
あなたの細胞を最もピュアな状態にリバースし、保管。
自身のiPS細胞を研究施設に提供し、Private
Bankとして保管。
-80度で冷凍保存。自身に治療が必要になった場合、
保管しているご自身のiPS細胞を使用して治療を受けることができます。

- 01 究極のリバースエイジング
-
病気を患うと自らのライフ スタイルに大きな影響を及ぼし、大切な家族にも負担が掛かります。 自分由来の抽出成分で病気にならない身体をつくります。

- 02 万が一の病気に備える
-
万が一大きな病気に掛かり、 承認済の治療方法があった場合、すぐに最先端の再生医療を受ける事が可能です。

- 03 難病の人々を救う
-
iPS細胞には、多くの種類があり、研究を促進する為には、たくさんのiPS細胞が必要です。あなたのiPS細胞を寄付する事で、多くの人を救う事が出来ます。
アクセス方法
ACCESS
東京ソフィア再生クリニック
〒104-0061
東京都中央区銀座7丁目3−6 銀座髙木ビル 7F
電車でお越しの場合
・東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線 銀座駅 C2出口より徒歩5分
・JR山手線・京浜東北線・東京メトロ銀座線 新橋駅 銀座口より徒歩7分
・JR山手線・京浜東北線・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 中央口より徒歩10分
車でお越しの場合
近くにコインパーキング有
※詳細は以下マップよりご確認ください
診療時間
10:30-13:00
14:00-18:00
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
